【完全解説】サッカーのゴールラインテクノロジーとは?仕組み・VARとの違い・日本での導入状況などを総まとめ!

①そのゴール、本当に入った?|疑惑のゴールシーンがきっかけに
サッカー観戦で最も盛り上がる瞬間――それはゴールが決まった時です。ところが「ボールがゴールラインを越えたかどうか」で判定が割れるシーンは、長年サッカー界を悩ませてきました。
特に有名なのが 2010年南アフリカW杯・イングランド vs ドイツ での“幻のゴール”。ランパードのシュートはクロスバーを叩いて明らかにゴールラインを越えましたが、ゴールが認められればイングランドが2-2の同点に追いついた場面で、「さぁこれから!」という流れの中で主審は得点を認めず、試合の流れを大きく変えてしまいました。結果、イングランドはこの疑惑の判定も響き、1-4で敗戦してしまいました。この誤審は世界中で議論を呼び、FIFAが「判定技術の導入」を真剣に検討するきっかけとなりました。
そこで誕生したのが ゴールラインテクノロジー(GLT:Goal-Line Technology)。ボールが完全にゴールラインを越えたかどうかを即座に判定し、審判に通知する革新的な仕組みです。現在では欧州の主要リーグやW杯でも導入され、サッカーの“公平性”を守る技術として注目されています。
本記事では、ゴールラインテクノロジーの仕組みや歴史、日本での導入状況、そしてVARとの違いについて徹底解説します。
💡サッカーテクノロジーの進化が凄い!半自動オフサイドテクノロジーがもたらすサッカーの未来⚽

② ゴールラインテクノロジー(GLT)とは?
ゴールラインテクノロジー(GLT:Goal-Line Technology) とは、サッカーにおいて ボールがゴールラインを完全に通過したかどうか を判定するための技術です。
サッカーの競技規則(第10条「1.得点」)には、「ボール全体がゴールポストの間、クロスバーの下を通過し、完全にゴールラインを越えたときに得点となる」 と定められています。しかし実際の試合では、選手や観客の位置からは判別が難しいことが多く、主審や副審の目視だけに頼るのは非常にリスクが高いのが現実でした。
💡サッカー競技規則第10条「試合結果の決定」を詳しく解説した記事はこちら↓

そこで登場したのがゴールラインテクノロジーです。スタジアムに設置されたカメラやセンサーがリアルタイムでボールの位置を追跡し、ゴールラインを完全に越えた瞬間に自動で判定。主審の専用時計に「ゴール」と表示され、誤審の余地を大幅に減らすことができます。
GLTの最大の特徴は 「即時性」と「客観性」。人間の判断ではなく機械が自動で判定するため、判定に時間がかからず、選手や観客もスムーズに試合に集中できます。これはVARのように映像を確認する仕組みとは異なり、サッカーの流れを止めずに判定が可能な点で非常に大きなメリットとなっています。
つまり、ゴールラインテクノロジーは「サッカーの最も大切な瞬間=ゴールの有無」を公平に、そして正確に守るために生まれたテクノロジーなのです。
③ ゴールラインテクノロジーの仕組み
ゴールラインテクノロジー(GLT)は、ボールがゴールラインを完全に越えたかどうかを 機械的に検知して即時判定するシステム です。その方式は大きく分けて2つ存在します。
🔹 カメラ方式(ホークアイ:Hawk-Eye)
- ゴール周辺に 7台以上の高速カメラ を設置し、ボールの動きを360度から追跡します。
- 撮影した映像を3D解析することで、ボールの位置をミリ単位で正確に把握。
- ゴールラインを完全に通過した瞬間を自動で判定し、1秒以内に主審の専用時計へ「GOAL」と通知します。
- テニスやクリケットでも使われる実績ある技術で、最も普及している方式です。
🔹 センサー方式(Cairos社など)
- ボール内部に マイクロチップ を埋め込み、ゴールポストやクロスバーには磁場を発生させるセンサーを設置。
- ボールがゴールラインを完全に通過すると磁場に変化が生じ、それをシステムが感知して判定します。
- 天候やカメラの死角に左右されにくく、環境が安定していれば高い精度を発揮します。
🔹 判定までの流れ
- ボールの位置をカメラまたはセンサーで常時追跡
- ボールが完全にラインを越えたかどうかを自動判定
- 判定結果が主審の腕時計にバイブと表示で通知される
このプロセスは 1秒以内 に完了し、選手・観客・解説者の誰もが判定を待つ時間を感じないほどスピーディーです。

🔹 VARとの違い
VARは映像を人間が確認するため、どうしても時間がかかることがあります。それに対してGLTは 自動判定 であるため、判定スピードと客観性に優れています。
つまりGLTは「ゴールの有無」に特化し、VARは「それ以外のプレー全般」をカバーするという役割分担になっています。
💡VARとは?最先端テクノロジーの進化がもたらすサッカーが向かう未来とは⚽
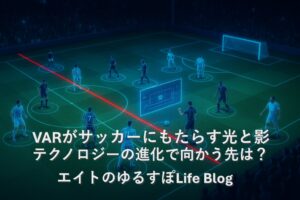
④ ゴールラインテクノロジー導入の歴史
ゴールラインテクノロジー(GLT)は、サッカー界の長い議論と誤審問題の積み重ねの中で誕生しました。
🔹 誤審から始まった議論
2000年代、W杯や欧州リーグでゴール判定をめぐる誤審が相次ぎました。特に①で紹介した 2010年南アフリカW杯 イングランド vs ドイツ戦 での“幻のゴール”は世界的な波紋を呼び、FIFAが「技術導入は不可欠」と判断する大きな転機となりました。
🔹 FIFAによるテストと承認
- 2011年:FIFAとIFABが複数の技術を実験的に検証
- 2012年:IFABが正式にGLTを競技規則に追加し、導入が認められる
🔹 世界初の公式導入
- 2012年12月:クラブワールドカップ(日本開催)で初採用。日本のスタジアムにGLTが設置され、世界中の注目を集めました。
🔹 欧州主要リーグへ拡大
- 2013-14シーズン:プレミアリーグが世界で初めてリーグ単位でGLTを導入
- 続いてブンデスリーガ、セリエA、リーグ・アンなども採用し、欧州では標準装備へ
🔹 W杯での本格採用
- 2014年ブラジルW杯:史上初めてGLTが正式採用
- フランス vs ホンジュラス戦でGLTによる判定が下され、世界中に強烈なインパクトを残しました。
- 以降のW杯ではGLTが常識となり、公平性向上に大きく寄与しています。
🔹 導入の流れまとめ
- 2000年代:誤審多発で議論開始
- 2012年:クラブW杯(日本)で初導入
- 2013-14:プレミアリーグが採用
- 2014年:W杯ブラジル大会で本格導入
- 現在:欧州主要リーグ・国際大会で標準技術に
GLTは、誤審をなくすための「サッカーの必然」として導入され、今や世界のトップレベルでは欠かせない存在となっています。
⑤ 誤審が変えた歴史的瞬間
ゴールラインテクノロジー導入の背景には、数々の“誤審事件”がありました。その中でも特に有名で、GLT導入の議論を加速させた事例をいくつか紹介します。
🔹 1966年W杯 イングランド vs 西ドイツ
- サッカー史上最も有名な「ゴールか否か」の判定。
- イングランドのハーストのシュートがクロスバーを叩き、ゴールライン付近に落下。主審はゴールを認め、イングランドはそのまま優勝。
- 「ウェンブリーの幻のゴール」として今も議論が続いています。
🔹 2005年 プレミアリーグ トッテナム vs マンチェスター・ユナイテッド
- ペドロ・メンデスのロングシュートがGKキャロルの手をすり抜け、明らかにゴールラインを越えたが、主審はノーゴール判定。
- この誤審はイングランド国内で大問題となり、技術導入の声が高まるきっかけに。
🔹 2010年W杯 南アフリカ大会 イングランド vs ドイツ
- ランパードのシュートがクロスバーを叩き、ゴールラインを大きく越えていたにも関わらずノーゴール判定。
- 世界中で批判が噴出し、FIFAがゴールラインテクノロジー導入を検討する決定的な契機となった。
🔹 2014年W杯 ブラジル大会 フランス vs ホンジュラス
- GLTが初めてW杯で正式採用された試合。
- フランスのシュートがゴールラインをかすめて判定が難しい状況だったが、GLTが「ゴール」と判定。
- 世界中が「技術の力で正確な判定ができる」と実感した瞬間となった。
このような誤審や判定の曖昧さがサッカーの歴史を左右し、その反省の積み重ねがゴールラインテクノロジー誕生へとつながっていきました。
⑥ 日本での導入状況|Jリーグでは多額のコストやスタジアム環境がネックに
世界の主要リーグや国際大会ではすでに標準化しているゴールラインテクノロジーですが、2025年現在、日本のJリーグではまだ導入されていません。
🔹 なぜ日本では導入されていないのか?
- 高額なコスト
- GLTの導入にはスタジアム1カ所あたり数億円規模の費用が必要。
- プレミアリーグやブンデスリーガのように資金力のあるリーグと比べ、Jリーグでは全クラブに導入するのは現実的に難しい。
- スタジアム環境のバラつき
- Jリーグはクラブごとに専用スタジアムや陸上競技場など環境が異なる。
- 全会場で同じ精度を確保するのが難しい。
- VARとの役割分担
- 2019年以降、日本でもVARが導入され、ゴール判定を映像で再確認できる仕組みが整った。
- そのため「GLTを導入しなくても一定の誤審防止は可能」という判断がなされている。
🔹 国内での議論と課題
- 国際大会(クラブW杯や日本代表の試合)を日本で開催する際には「GLT設置が必須」となるケースがあり、そのたびに議論が浮上。
- ファンや解説者からは「公平性のために導入すべき」という声がある一方で、「費用対効果に見合わない」との意見も根強い。
🔹 将来的な見通し
- Jリーグがさらなる国際化を進める中で、ビッグクラブの本拠地や新設スタジアム から段階的にGLTが導入される可能性は十分にある。
- 2020年代後半に日本がW杯や国際大会を招致する場合、GLT導入は避けられないテーマとなる可能性はある。
つまり、日本におけるゴールラインテクノロジーの課題は「コスト」と「スタジアム環境」の2点に集約されます。技術的にはすでに可能でも、経済的・運営的な要因で導入が遅れているのが現状です。
⑦ ゴールラインテクノロジーのメリットと課題
ゴールラインテクノロジー(GLT)は、サッカーの判定を公平にするための大きな前進ですが、万能ではありません。ここではそのメリットと課題を整理します。
✅ メリット
- 誤審防止で公平性が向上
- ゴールか否かという最も重要な判定を正確に下せるため、試合の信頼性が高まる。
- 主審・副審の負担軽減
- 人間の目では見えにくい瞬間を技術が補完。審判が「正しい判定かどうか」で悩む時間を減らせる。
- 試合の流れを止めない即時判定
- VARのように長時間の映像確認を必要とせず、わずか1秒以内に結果が通知される。観客や選手のストレスも軽減。
- 観客・選手の納得感アップ
- 「誰が見てもゴール」という明確な証拠が残るため、試合後の議論や不満を減らす効果がある。
⚠️ 課題
- 高額な導入コスト
- スタジアム1会場あたり数億円の投資が必要。財政基盤の弱いリーグやクラブには導入が難しい。
- スタジアム環境の制約
- 陸上競技場や古い施設では設置が困難。全試合で統一運用するのが難しい。
- 下部リーグや育成年代では非現実的
- FIFA基準を満たす設備はアマチュアや地域リーグでは導入不可能。結果として「技術のある試合」と「ない試合」で不平等が生まれる懸念。
- 「テクノロジー頼み」への懸念
- 一部からは「人間の誤審もサッカーの一部」「テクノロジーに頼りすぎるとサッカーの魅力が薄れる」との声もある。
ゴールラインテクノロジーは、公平性を守る強力な武器である一方、コストや運営面での課題が残っています。特にJリーグのようにクラブごとの環境差が大きいリーグでは、導入のハードルが高いのが現状です。
⑧ VARとの違い
ゴールラインテクノロジー(GLT)とVAR(ビデオ・アシスタント・レフェリー)は、どちらも「誤審を減らすための技術」ですが、その役割は大きく異なります。GLTはゴール判定に特化したシステムであり、VARは幅広いプレーを映像で確認できる仕組みです。
以下の表に両者の違いを整理しました。
| 項目 | ゴールラインテクノロジー(GLT) | VAR(ビデオ・アシスタント・レフェリー) |
|---|---|---|
| 判定対象 | ゴールの有無のみ(ボールが完全にラインを越えたか) | ゴール、オフサイド、ファウル、カード判定など幅広いプレー |
| 判定方法 | 自動判定(カメラ・センサーで即時通知) | 人間が映像を確認し、主審に助言 |
| 判定スピード | 1秒以内に主審の時計に通知 | 映像確認が必要なため数十秒〜数分かかる場合もある |
| 精度・客観性 | 機械による完全判定で主観が入らない | 最終判断は人間が行うため主観の余地あり |
| 試合への影響 | 試合の流れを止めない | 試合が一時中断することが多い |
| 導入状況 | 欧州主要リーグ・W杯などで標準化 | W杯・Jリーグ含む多くの主要大会で導入済み |
🔹 GLTとVARは互いに補完し合う存在
- GLTは「ゴールに特化した即時判定システム」
- VARは「広範囲をカバーする審判支援ツール」
両者は競合するのではなく、互いに補完し合う存在 としてサッカーの公正さを守っています。

⑨ 今後の展望 ― AIとゴールラインテクノロジーの融合
ゴールラインテクノロジー(GLT)はすでに高い精度を誇っていますが、今後は AI(人工知能)や高度なデータ解析技術 と組み合わせることで、さらに進化していくと考えられます。
🔹 AIによる判定精度の向上
従来はカメラやセンサーが「ラインを越えたかどうか」だけを検知していましたが、AIを活用することで以下のような高度な解析が可能になります。
- ボールの軌道やスピードを予測し、ゴールに至る瞬間をより正確に捉える
- 悪天候や選手が重なったシーンでも映像を補正し、誤判定の可能性をさらに低下させる
- 画像処理+機械学習により、人間の目では見えない細かい動きを認識
🔹 VARとの統合・自動化
将来的にはGLTとVARを単独のシステムとして運用するのではなく、AIによって統合された「自動判定プラットフォーム」 として発展する可能性があります。
- ゴール判定(GLT)はAIが即時判定
- ファウルやオフサイドもAIが一次判定し、VARは最終確認のみ
- これにより判定のスピードと正確性がさらに高まり、試合の中断時間を短縮
🔹 リアルタイムデータ活用
AI解析で得られた情報は、判定だけでなく「試合データ」として観客やメディアにリアルタイム配信される未来も近いでしょう。
- ゴール判定の瞬間をCGで即座に再現
- ボール位置や通過ラインをテレビ・スタジアムスクリーンで共有
- ファンも納得できる“見える判定”として、エンタメ性も向上
🔹 より公正でよりスムーズな試合運営が可能に
ゴールラインテクノロジーは「ゴールか否か」の正確な判定を支える技術ですが、AIとの融合により「精度」「スピード」「透明性」のすべてが進化します。未来のサッカーでは、AIが審判を強力にサポートし、より公正でスムーズなゲーム運営が当たり前になるかもしれません。
⑩サッカーを変える一線 ― ゴールラインテクノロジーの現在地と未来
ゴールラインテクノロジー(GLT)は、サッカーにおける最重要判定「ゴールか否か」を正確かつ即時に判定するために生まれた技術です。
- 仕組み:カメラ方式やセンサー方式でボール位置を追跡し、自動で判定
- 歴史:2012年クラブW杯(日本開催)で初導入、2014年W杯から本格採用
- 事例:数々の誤審がきっかけとなり、導入が加速
- 日本の現状:Jリーグでは未導入。理由は高額なコストとスタジアム環境の制約
- メリット:誤審防止、公平性向上、審判負担軽減、試合の流れを止めない
- 課題:導入コストの高さ、すべての大会で統一運用できない点
- VARとの違い:GLTはゴール判定に特化、VARは広範囲を映像で確認。両者は補完関係
- 未来:AIとの融合でさらに精度・スピード・透明性が進化する可能性
ゴールラインテクノロジーは、サッカーの公正さを守るために欠かせない存在へと成長しています。今後も技術の進化とともに、その役割はますます重要になっていくでしょう。
💡初心者も経験者もこれ一択!サッカー用語をまとめた辞典機能のある解説記事はこちら↓(この記事で出てきた用語もあります)
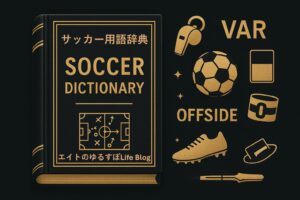
💡スポーツの疲労軽減、リカバリー、睡眠の質向上に興味のある方はTENTIAL BAKUNEもおすすめ!
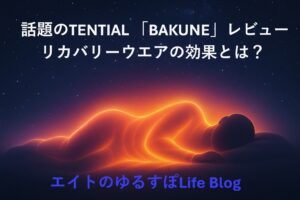
 エイト
エイトこの記事が参考になったよという方はXのフォロー、サイトのブックマークなど応援してくださると、とても嬉しいです😄
↓ランキングに参加しています♬良かったら覗いてみてください↓
にほんブログ村

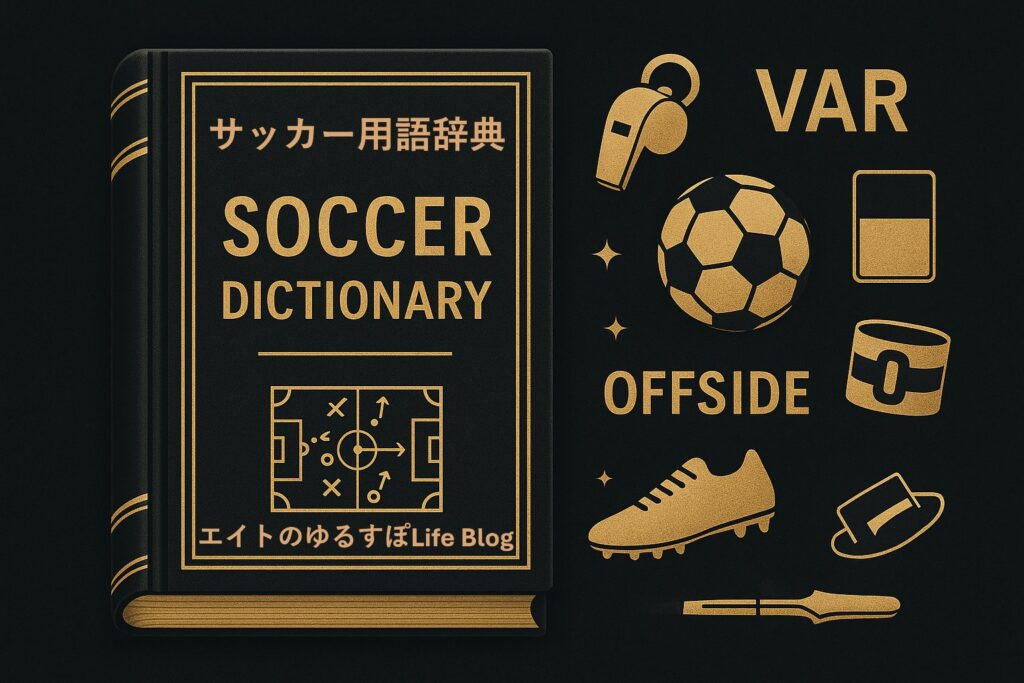

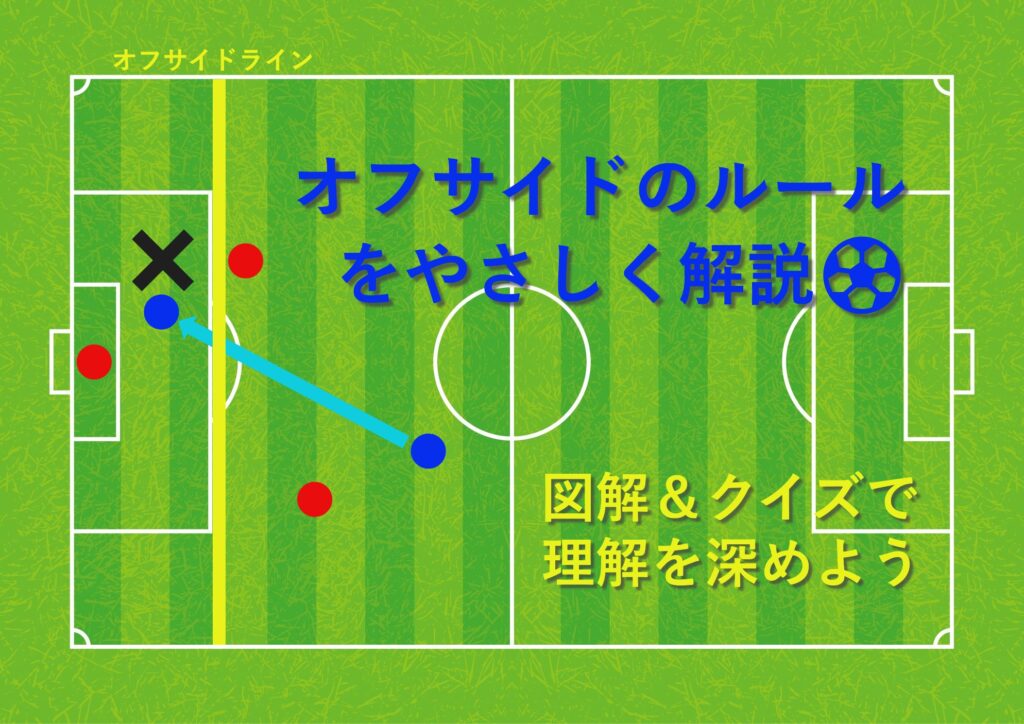


コメント