サッカーのDOGSOを完全攻略!VARが介入する本当の理由|動画実例付きで理解が深まる💡

①DOGSO(ドグソ)とは?決定的得点機会を奪う“最も重い反則”を徹底解説!
サッカー中継や試合解説で耳にする「DOGSO(ドグソ)」というワード。
これは「Denial an Obvious Goal-Scoring Opportunity(決定的得点機会の阻止)」の略称で、主審がレッドカードを提示する重大な反則の一つです。
例えば、決定的な場面のゴール前で相手選手を後ろから倒したり、手でシュートをブロックしたり…。
そんな“明らかにゴールになりそうなプレー”を止めてしまった行為がDOGSOに該当します。
本記事では、
✅ DOGSOの意味とルールの原則
✅ 実際にDOGSOと判断されるプレー例
✅ SPAとの違いやVARとの関係性
…などをわかりやすく解説します!
これを読めば、試合中のレッドカードの意味がより深く理解できるはずです⚽
💡スポーツでの疲労回復に一役買う「リカバリーウエア」の解説記事はこちら↓睡眠の質改善に!
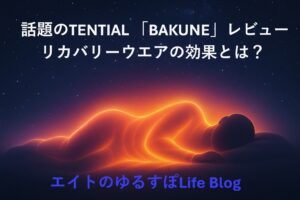
②DOGSOの定義と適用される条件とは?
「DOGSO(決定的得点機会の阻止)」は、相手チームのゴールが明らかに決まりそうな場面で、反則によってそれを妨げる行為を指します。
これはサッカー競技規則第12条「ファウルと不正行為」に明記されており、非常に重い反則として扱われ、通常はレッドカード(退場)の対象となります。
💡サッカー競技規則第12条「ファウルと不正行為」を詳しく解説した記事はこちら↓

では、どんな状況が「決定的得点機会」と判断されるのでしょうか?
以下の4つの条件をすべて満たすと、DOGSOと判定される可能性が高くなります👇
✅ DOGSOの4つの判断基準(通称「4DOGSO」)
- プレーの方向
攻撃側選手がゴール方向へ向かっているかどうか。 - ファウルの位置
ゴールとの距離が近いほどDOGSOが成立しやすい。 - ボールのコントロール可能性
攻撃側選手がボールをコントロールしていた、またはコントロールできる状況か。 - 守備側選手の人数
ゴールと攻撃側選手の間に他の守備者(GKを含む)がいない、または影響を与えられない状況か。
これらを主審が総合的に判断し、「明白な得点機会を反則で阻止した」とみなされた場合、DOGSOとして処分されます。
試合を大きく左右する重大な判定のため、VAR(ビデオ・アシスタント・レフェリー)が介入するケースも多いルールです。
💡DOGSOとも関わり深いVARを詳しく解説した記事はこちら↓
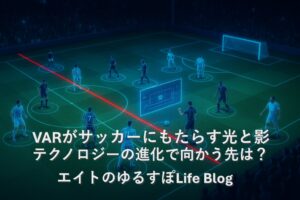
③DOGSOが適用される典型的なプレー例
DOGSOは、審判が「このままなら確実にゴールだった」と判断するような状況での反則に適用されます。
では、具体的にどのようなプレーがDOGSOとされるのでしょうか?
代表的なケースを紹介します。
🟥ケース①:後方からのスライディングで倒す(ペナルティエリア外)
ゴールへ向かってドリブルしていた選手を、最後尾のディフェンダーが背後からスライディングして倒す。
👉 DOGSO認定 → レッドカード+直接フリーキック
※明らかに1対1の状況で、守備側に他の選手がいない場合がポイント。
🟥ケース②:ゴールキーパーがペナルティエリア外でハンド
飛び出したGKがエリア外で手を使い、シュートやパスを防いだ場合。
👉 DOGSO認定 → レッドカード+直接フリーキック
🟥ケース③:意図的なハンドブロック
守備側選手がゴールに向かうシュートを手や腕でブロックして止めた場合。
👉 DOGSO認定 → レッドカード+PKまたはFK
🟨例外:ペナルティエリア内での「正当なチャレンジ」は“イエロー”に緩和
2016年のルール改正で話題となったのが、いわゆる「三重罰(トリプル・パニッシュメント)」の見直しです。
これは従来、ペナルティエリア内でのDOGSOに対して適用されていた
「PK+レッドカード+次節出場停止」という、影響の大きすぎる3つの処分を緩和する目的で導入されました。
現在のルールでは、以下のようなケースではイエローカードでの処分に軽減されます👇
🔹ケース例:
ゴール前でDFがスライディングタックルを試み、明らかにボールをプレーしようとしたが、結果的にファウルとなってしまった場合。
👉 主審の判断で「正当なチャレンジ」と認定されれば、PK+イエローカード(警告)にとどまります。
ただし、ボールに対するプレー意図が見られない場合(例:後方からの引っ張りや突き飛ばし、手や腕による妨害など)は、依然としてレッドカード(退場)が適用されます。
つまり、「正当なチャレンジかどうか」が判断のカギを握るポイントです。
このルール変更によって、試合の流れや選手の立場に配慮したよりバランスの取れた裁定が可能となりました。
💡ペナルティキックのルールや基本などを動画などで詳しくわかりやすい解説した記事はこちら↓

④DOGSOとSPAの違いとは?混同しやすい反則を整理!
サッカーには似たような場面で発生するファウルが多数存在しますが、特に混同されやすいのが
DOGSO(決定的得点機会の阻止)とSPA(有望な攻撃の阻止)の違いです。
どちらもファウルによって相手のチャンスを潰す反則ですが、決定的な違いは「ゴールの可能性の高さ」にあります。
🟥 DOGSO(ドグソ)=「明白な得点機会の阻止」
- ゴールがほぼ確実に決まりそうな場面での反則
- 例:GKと1対1の場面で後方から倒す/シュートをハンドでブロック
- 原則:レッドカード(退場)+PKまたはFK
🟨 SPA(エスピーエー)=「有望な攻撃の阻止」
- ゴールに直結するほどではないが、チャンスになりそうな場面を潰す反則
- 例:カウンターを止めるための“戦術的ファウル”など
- 原則:イエローカード(警告)+FKまたはPK
✅ DOGSO・SPA比較表
| 項目 | DOGSO(ドグソ) | SPA(スパ) |
|---|---|---|
| 意味 | 決定的な得点機会の阻止 | 有望な攻撃の阻止 |
| ゴールの可能性 | 非常に高い(ゴール目前) | 中程度(チャンスの芽) |
| 主な状況 | 1対1の抜け出し、ハンドブロックなど | カウンター阻止、ドリブル中の故意ファウルなど |
| 主な処分 | レッドカード(退場) | イエローカード(警告) |
| PKとの関係 | PK+レッド(※正当チャレンジ時はイエロー) | PK+イエロー |
💡ポイント解説:
- DOGSOは「決まりそうなゴールを止めた」行為
- SPAは「チャンスを潰した」程度の行為
- 主審の裁量が大きく、VARも含めた判断材料が求められる重要な判定です
この違いを知っていると、試合中のファウルの重みがよりリアルに理解でき、観戦の面白さもグッと増します!
💡SPAをもっと詳しく知りたい方は関連記事のこちらから↓

⑤DOGSOはVARでどう判断される?主審の視点と判定の流れ
DOGSO(決定的得点機会の阻止)は、試合を左右する重大な反則であり、誤審が許されないシーンでもあります。
そのため、近年ではVAR(ビデオ・アシスタント・レフェリー)が、DOGSOに関する判定にも頻繁に関与します。
🔍 VARが介入するDOGSOの主なケース
以下の4つの状況では、VARがチェック対象となり、主審に映像確認を促す(オン・フィールド・レビュー)ことがあります👇
- DOGSOによるレッドカードの有無(出すべきか、取り消すべきか)
- ハンドやファウルの位置がペナルティエリア内か外か
- 実際に決定機だったかどうか(4つのDOGSO要件)
- 明確な誤審があった場合の訂正
✅ 主審がDOGSOを判断する際の基準(再確認)
DOGSOの判定には、以下の4要素をもとに総合的に判断します:
| 要素 | 判断基準の詳細 |
|---|---|
| ① ゴールまでの距離 | 近いほどDOGSOの可能性が高い |
| ② 攻撃の方向性 | ゴールへ向かっていたかどうか |
| ③ ボールコントロールの可能性 | ドリブルやトラップでコントロールできた状況か |
| ④ 他の守備選手の位置 | カバーできるDFやGKがいたかどうか |
これらがすべて揃っていると、DOGSOが成立しやすくなります。
🎥 VARが介入したDOGSOの実例
💡イエローカード判定がVARによりDOGSO認定されレッドカード判定に覆った事例↓
💡まとめポイント
- DOGSOはレッドカードに直結するため、VARのチェック対象として非常に重要
- 主審は「一瞬の判断」と「4要素の総合評価」で判定を下す
- 映像確認によって、誤審リスクを軽減し、公平性を保つ役割がある
⑥DOGSOを知れば、サッカー観戦がもっと深く面白く!
「DOGSO(決定的得点機会の阻止)」は、サッカーのルールの中でも最もインパクトの大きい反則のひとつです。
レッドカードによる一発退場やPK判定、そしてVARの介入など、試合の流れを劇的に変える重大な瞬間に関わるルールでもあります。
本記事では、
- ✅ DOGSOの意味とルールの根拠
- ✅ 適用されるプレーの実例と注意点
- ✅ SPAやVARとの関係性
…を整理してきました。
DOGSOの判定基準やVARの役割を知っていれば、
ただ「レッドカードが出た」と見過ごすのではなく、
「なぜその判定が出たのか?」を理解しながら観戦することができ、サッカーの楽しみ方が一段と深まります⚽
今後、試合でDOGSOやSPAが出たときは、ぜひこの記事で紹介したポイントを思い出してみてください!
💡初心者も経験者もこれ一択!サッカー用語をまとめた辞典機能のある解説記事はこちら↓(この記事で出てきた用語もあります)
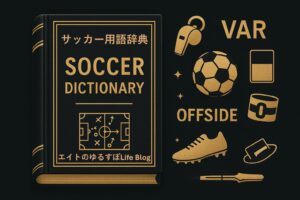
 エイト
エイトこの記事が参考になったよという方はXのフォロー、サイトのブックマークなど応援してくださると、とても嬉しいです😄
↓ランキングに参加しています♬良かったら覗いてみてください↓
にほんブログ村

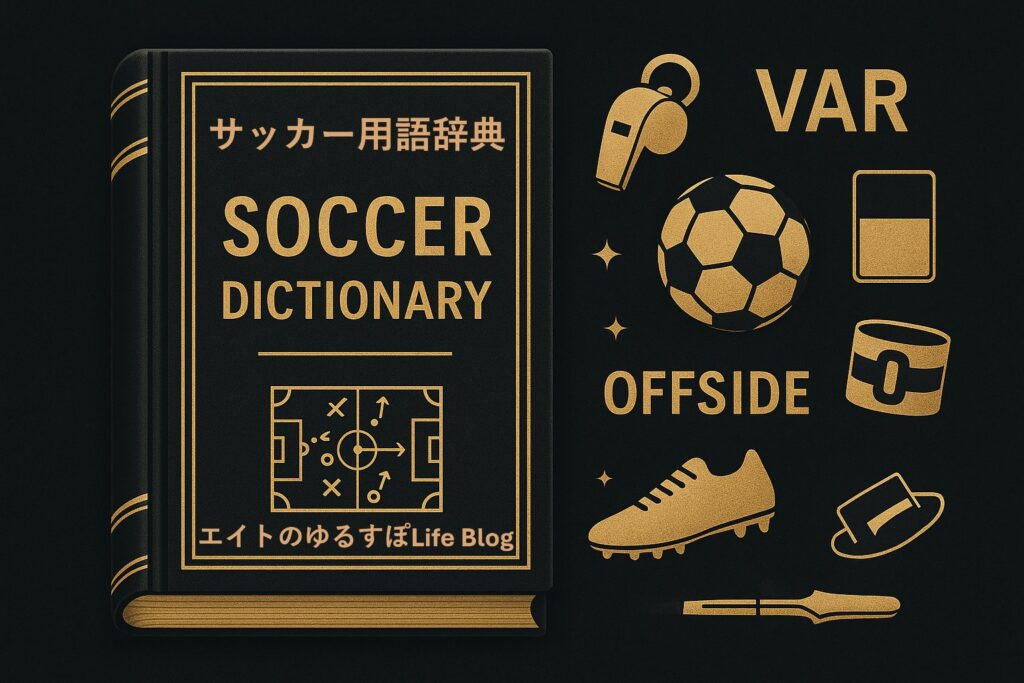

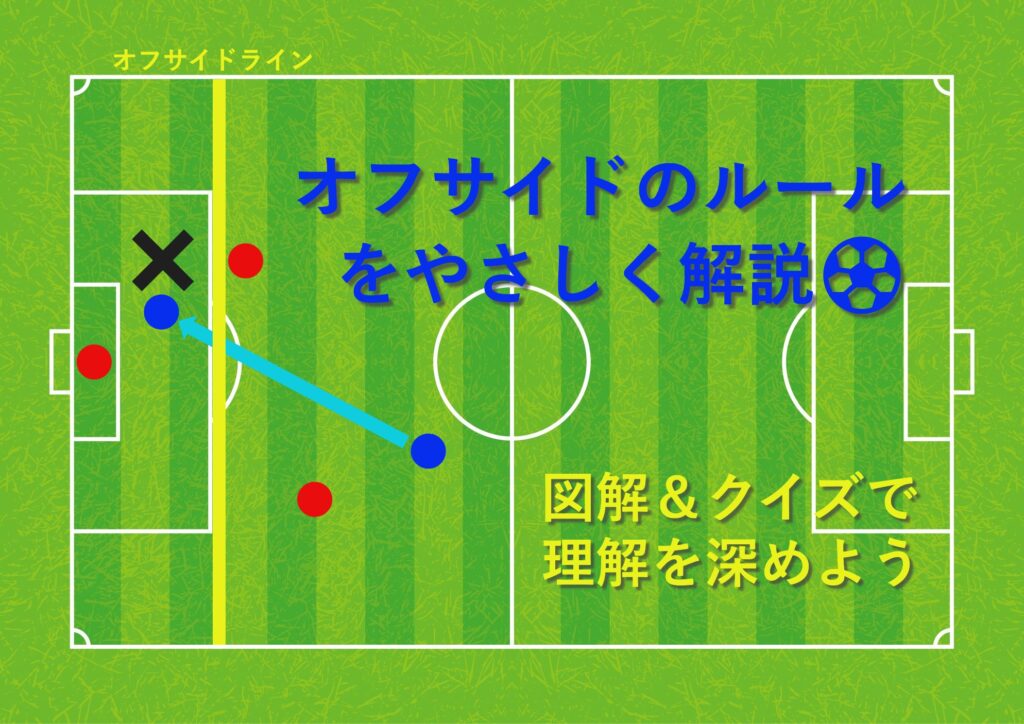


コメント